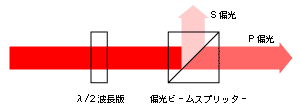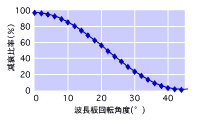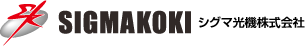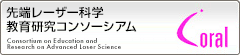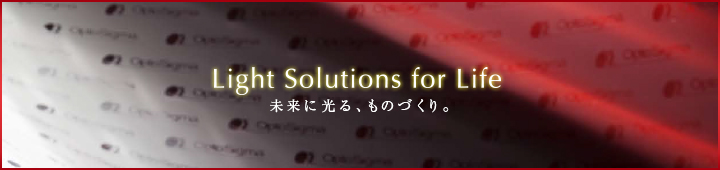
- HOME >
- コミュニティ >
- 光学屋さんのまめ知識 >
- 014 レーザの光量調整
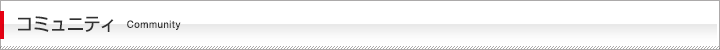
レーザによる加工・測定を行なう場合「出力の安定性」が重要なポイントになります。
そこで今回は「レーザの光量調整」をテーマとしたまめ知識を。
レーザの種類によっては出力調整機能が付属しており、加工の状況やセンサの受光感度に合わせてレーザ側で出力値の調整をすることが出来ます。「じゃぁ、それで十分じゃないか」と思われるかもしれませんが、それで済んだらシグマ光機の出番はありません(笑)。実際に加工や測定を行う際にレーザ側で出力調整を行うと、実に様々な問題が出てきてしまうのです。
例えば
定格の範囲内であっても、出力レベルを下げていくと出力値が不安定になる場合がある→安定した加工ができない
光軸のズレが生じる場合がある→出力を調整する度に光軸調整が必要
といった問題です。
こうした問題を解決するために、レーザは安定した領域で出力を維持し、
外部の光学製品で光量の調整をすることが必要となるのです。
光量調整に使用される一般的な光学部品と言えば「ND(ニュートラルデンシティ)フィルター」でしょう。
「NDフィルター」は大きく2種類に分類できます。光学ガラスに吸収剤を混ぜた「吸収型」と、クロム膜を施した「反射型」です。さらに減衰率が固定されている「固定式」と、コーティングをグラデーション状に施すことで1枚の素子の中で減衰率を連続的に変化させた「可変式」とが存在します。その名の通り光学的に「中性」で波長依存性が少ないので、色彩に影響を与えません。このため非常に汎用性の高い光量調整部品であると言えます。

段階的な光量調整であれば、減衰率に応じた固定式NDフィルターを複数枚用意し、ホルダー等で切替えることで実現は可能です。しかし、複雑な光量制御を必要とする加工機用途等の場合は連続的な光量調整が不可欠です。
確かに「可変式NDフィルター」でも連続的な調整は出来ますが、グラデーション状にコーティングされているため、ビーム内で光量のムラが発生します。特にビーム径が大きくなる程影響は顕著で、折角ビーム品質の良いレーザを使用しても無駄になってしまうのです。

では、連続的な光量調整が可能で、なおかつビーム品質の維持が可能な方法とはどのようなものでしょうか。
シグマ光機では加工機用のアッテネータ(減衰器)として次の2つの方法を用いた「バリアブルアッテネータ」を提案しています。
バリアブルアッテネータ(プレート回転タイプ)
特殊な膜を付けたガラス基板を回転させる事により、透過率(反射率)を変化させます。
ビームがガラス基板を通過する際に発生する光軸シフトを解消するため、光軸シフト補正基板(平行平面基板)を配置し、透過率(反射率)を制御するガラス基板に対して対称方向に回転させることで光軸シフトを補正します。
ガラス基板の回転機構に自動ステージを組込むことで、ステージコントローラを介してPCによる光量の外部制御が可能になります。
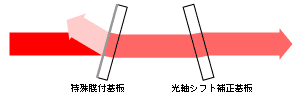
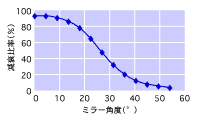
バリアブルアッテネータ(偏光キューブタイプ)
偏光ビームスプリッターの手前でλ/2波長板を回転させる事により、透過率(反射率)を変化させます。
キューブタイプの偏光ビームスプリッターを使用する為、光軸のシフトも最小限に抑えられます。
µ/2波長板の回転機構に自動ステージを組込むことで、ステージコントローラを介してPCによる光量の外部制御が可能になります。
シグマ光機ではお客様の仕様に合わせて最適なバリアブルアッテネータをご提案いたしますので、是非営業部までお問合せください。
関連製品:NDフィルター→WEBカタログ
関連製品:バリアブルアッテネータ(プレートタイプ)→WEBカタログ
関連製品:バリアブルアッテネータ(偏光タイプ)→WEBカタログ