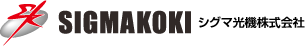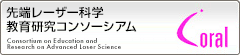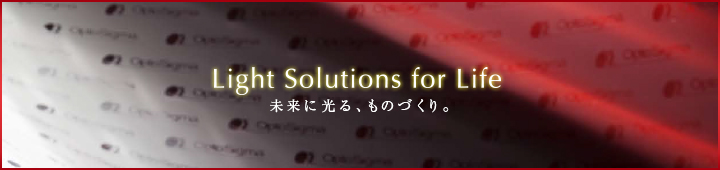
- HOME >
- コミュニティ >
- 光学屋さんのまめ知識 >
- 020 干渉
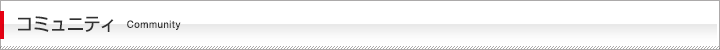
内政干渉。生活を干渉される。親の干渉。
世間一般的に『干渉』と言う言葉には、あまり良い印象は無いようです。
でも、光の世界では、精密測長や平面度計測など、ちょっと役に立つことがあるようです。

水が入ったバケツを蹴ると、バケツの水が同心円状に波立ち、中心で大きく盛り上がるのを経験したことがあると思います。
これが、波の干渉です。
波の山と山が重なると波は高くなり、谷と谷が重なると波は低くなります。山と谷が重なると波は打ち消し合い、元の水面の高さになります。

光の場合は、1つの光源から出た光が、2つの光束に分割され、その後再び重なった時に干渉が発生します。
下の図は2つの平行ビームが重なったときの干渉のシミュレーションです。
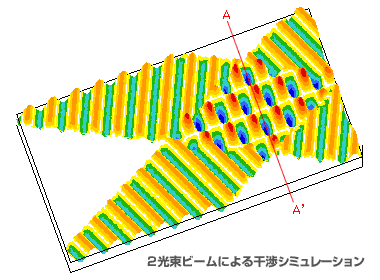
左から右に2つの波が進み、角度を持って交差しています。交差した部分で干渉現象が見られます。
注意して見ると、交差した部分の中に変化していない筋(白色)が3本あります。
光は、波の振れ幅大きければ大きいほど、明るく見えます。よって、変化がない筋は暗い部分として観測されます。干渉が起きている部分に垂直に紙を入れると左の図の様な明暗の縞が観察されます。これが干渉縞です。
ここで、不思議なことが起こります。元の光の明るさを1とすると、2つの光が重なった部分の明るさは1+1=2のはずです。
しかし、干渉縞の明るい部分は元の光の明るさの4倍の明るさになります。
1+1=4・・・?暗い部分は1+1=0なので、エネルギー保存の法則には反していないようですが・・・。
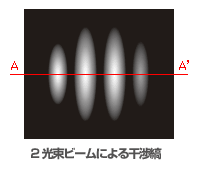
ところで、光は世の中に満ち溢れているのに、何故、光の干渉を身近に感じることができないのでしょうか?今まで述べてきたように干渉の現象は単純で、どこにでも出現しそうな現象です。しかしながら、実際に光の干渉現象を実感できるのは、レーザを使っている人ぐらいです。
この答えは、いずれこのスペシャルで取り上げます。お楽しみに。
参考文献
Max Born and Emil Wolf著/草川 徹 訳:「光学の原理II」第7版,東海大学出版