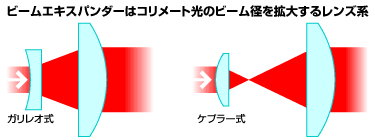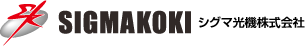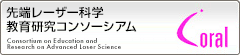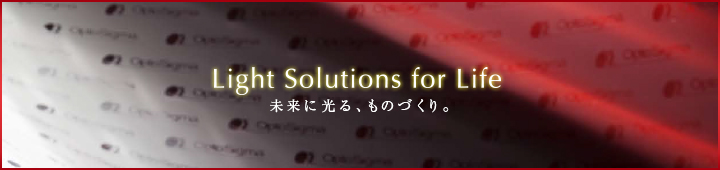
- HOME >
- コミュニティ >
- 光学屋さんのまめ知識 >
- 004 コリメート
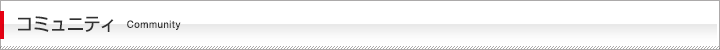
今回は、光学系を組む際の重要な光学調整の一つである「コリメート」がテーマです。
レーザ光の大きな特徴として、空間をほぼ一直線に進ませることができるという、高い指向性が挙げられます。
しかし、レーザの光をより遠くまで届かせるためには、長い距離を伝播しても拡がったり収束したりしない平行な光束にする必要があります。このため、ミラーによる反射やレンズによる屈折を用いてビーム光が平行状態になるよう光学調整を行います。この調整を「コリメート」と言い、また平行状態に調整されたビーム光を「コリメート光」と呼びます。
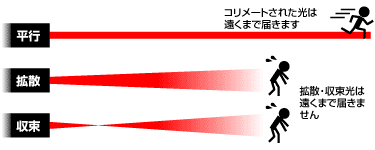
ただし、実際には完全な平行光線束というのは存在せず、どんなにコリメートされたレーザ光でも波動光学で知られるところの回折の影響を受けて、遠方に進むにつれて僅かずつビームが拡がって行きます。この拡がりの程度は、ビーム拡がり角(Δθ)や波面の曲率半径(r)といった数値で表されるのが一般的です。
光学系を構築する上では、光路の途中でビーム径の拡大・縮小が必要になる場合が有ります。例えば、小さなスポットに効率良く光を絞込んだり、広い面の干渉縞を観察したりするためには、大口径のコリメート光を得ることが必要です。
ビーム径の拡大には通常2枚のレンズを使用し、入射側のレンズで一旦ビーム光束を拡散させて広げた上で、出射側のレンズで再度コリメート状態へと調整します。
ビームエキスパンダーは、コリメート光をコリメート光のままで一定の倍率に拡大するために設計されたレンズ系で、凹レンズと凸レンズを組合わせたガリレオ式と、凸レンズ同士を組合わせたケプラー式とが有ります。また、ディオプター補正機能付のビームエキスパンダーであれば、一定の倍率に拡大するだけでなく収束・拡散の調整も可能です。
なお、ビームのコリメート状態を確認するには、シェアリング干渉計を応用した
ビーム用コリメーションチェッカーを使用すると効率的です。
参考:ビームの平行状態を簡単にチェックできるツールを探せ!