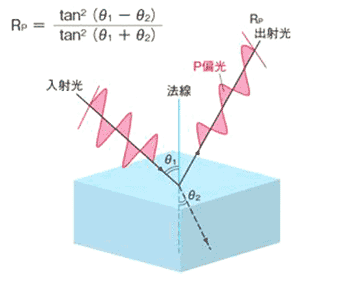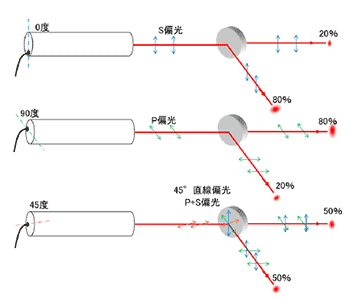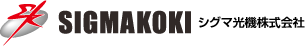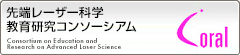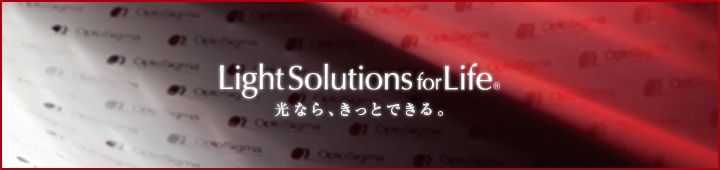
- HOME >
- コミュニティ >
- ちょっとためになる光学勉強会 >
- ビームスプリッター
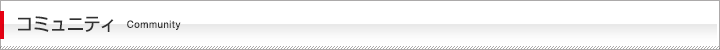
ただのガラス板と片付けないでください。
この光学素子は光学系の中で重要なミッションを受け持っています。
例えば、光計測で、ビームスプリッターで分けられた一方をリファレンスとしてモニターすることで、もう一方のビームを使った光の計測の精度を上げることができます。
また、顕微鏡でもビームスプリッターを使って、照明光で試料を明るく照らすことと、試料を拡大観察する系を両立させています。
さらに、干渉計を始めとする波動光学を使った光学系では、ビームスプリッターが無ければ、我々は光の波長の恩恵にあずかることはなかったでしょう。
最近話題になっている、量子コンピュータに置いても、ビームスプリッターは重要な役割を担っています。
光子の2つの状態を重ね合わせ*1る場合や複数の光子のもつれ状態*2を起こさせるキーデバイス(?)として、活躍しているようです。
ビームスプリッターは文字通り、レーザビームを2本に分けたり、分けた2本のビームを重ね合わせることに使用されます。
ビームスプリッターにはキューブタイプとプレートタイプの2種類があります。
どちらの方が良いのでしょうか?
これは、実験の目的によって変わってきます。
コンパクトにまとめる場合はキューブタイプを使うことが多いようです。
逆に、大きなビームを使用する場合は、プレートタイプの方が軽量化でき、キューブタイプと比べて費用も格段に安くできます。
この他に、それぞれの長所、短所を考慮した使い方があります。
プレートタイプは45°傾けて使用するので、屈折によって入射ビームが少し横ずれを起こします。
プレートの厚みや屈折率によっても変化しますが、一般的なBK7のガラス基板(屈折率 1.52)で厚さ 3mmであれば、横ずれ量は1mm程度です。
細めのビームを使って、ビームスプリッターを光学系に抜き差しするような場合は、ビームスプリッターを入れるたびに光路がシフトし、ターゲットとビームが重ならなくなってしまうことがあります。
一方、キューブタイプは入射ビームに対し垂直で当たる面が複数あります。
もちろん、ビームが入出射する4面には反射防止膜がコートされています。
それでも、0.1〜0.5%反射がおき、反射光が光源の方に迷光として戻ってしまいます。
パワーが強いビームの場合には、4面すべての反射光が確認される場合もあります。この反射光がレーザの共振器内に戻ると、レーザの発振は不安定になり、メインのレーザ出力にノイズを生じさせることになります。
キューブをわずかに傾けて反射光を取り除ける場合は良いのですが、ビームが太く観察画像の中に映りこんでくる場合は厄介です。
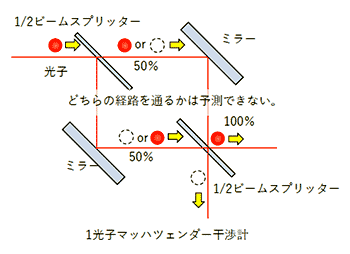
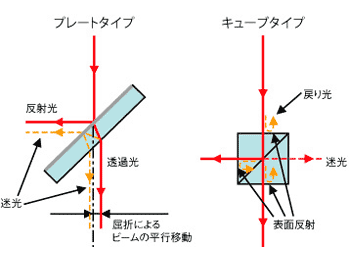
プレートタイプはビームスプリッター単独では光源側には反射しないので、絶対にレーザ側に反射光を戻したくない場合は好都合です。
ビームスプリッターを使用するときに最も気を付けなければならないことがあります。
それは、偏光特性です。
「偏光は良く分からない。」「この実験は偏光は関係ない。」と言う人もいるかもしれませんが、実験にレーザを使用する限りビームスプリッターの偏光特性を無視することはできません。
それでも、厄介なことに関わりたくない方は、ちょっと高価ですが、無偏光キューブハーフミラー(NPCH)やハイブリッドキューブハーフミラー(HBCH)を使ってください
このビームスプリッターを使っている限りは、どんな偏光状態の光が入ってきても、透過光と反射光で1:1に分割してくれます。
反対に、レーザビームで安価(?)なハーフミラーを使用する場合は、透過光と反射光は1:1に分けれていないはずです。
これは、反射面に45°の角度でビームが入射するとP偏光とS偏光と言う2つの光の成分(偏光)が生じるからです。
S偏光は反射面を45°に傾けた回転軸と同じ方向に向いている直線偏光、P偏光はS偏光に垂直な方向の直線偏光のことです。
反射光はこのP偏光とS偏光で反射の法則が異なるので別々に考えなければなりません。
反射膜によっては、P偏光の時は20%でS偏光の時は80%と言う場合も出てきます。
レーザ光のように直線偏光ではない光の場合、P偏光とS偏光は同じ量に分配されます。
反射率は、P偏光が20%でS偏光が80%であっても、平均されて50%になります。
しかし、レーザ光は直線偏光で出てきます。
今、縦方向の直線偏光でハーフミラーに入射したとすると、ハーフミラーのS偏光の方向と一致するので、S偏光の方向に100%、P偏光に0%が分配されます。
よって、ハーフミラーで反射される反射率80%と言うことになります。
透過率は残りの20%になるので、80:20なのにハーフミラーと言う不一致が生じます。
レーザが円筒形であれば、光軸中心に回転させることで、偏光方向を自由に選ぶことができます。
90°回転で、透過率と反射率が反転させることができます。そして、45°回転であれば、晴れて、P偏光とS偏光は同じ量に分配され、ハーフミラーとなります。
四角いレーザの場合はどうするか?45°傾けて設置するわけにいかないので、偏光方向を変えることができる1/2波長板と言う素子をレーザとハーフミラーの間に入れます。
これはもう、偏光実験とほとんど変わりません。
だから、最初に言った「偏光に関わりたくなければ、無偏光のタイプのハーフミラーを選定しなさい。」と言う理由が分かってもらえたと思います。
いつまでも、関わらずにいられれば良いのですが、偏光の足音が近づいてきているような気がします。
*1 マクロな世界では生じない量子力学特有の現象。光子の「0」と「1」の2つの状態を同時に重ね合わせることができる。
*2 マクロな世界では生じない量子力学特有の現象。重ね合わせ状態の光子が2つある場合、どちらか一方の値が観測により決まると、もう一方の光子の値が決まってしまう関係にあるとき光子がもつれていると言う。
S偏光の反射の法則
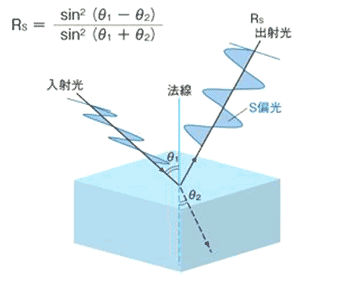
P偏光の反射の法則