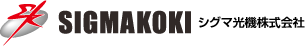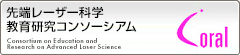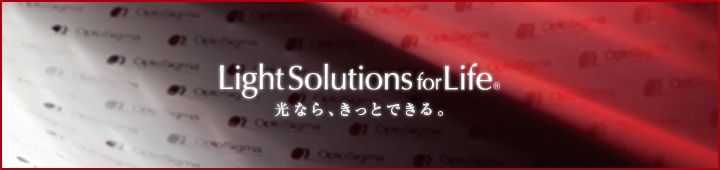
- HOME >
- コミュニティ >
- ちょっとためになる光学勉強会 >
- レーザ安全 2回目 レーザ安全の規格
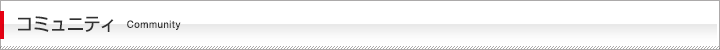
JIS規格は皆さんご存知だと思います。
鉛筆の硬さから航空機の設計まで、日本の工業製品に関するあらゆるものを定めた国家規格です。
レーザに関する規格もいくつかあります。その中の1つに、JIS C6802「レーザ製品の安全基準」があります。
この中に、レーザを使うための安全対策が書かれていると思うかもしれませんが、残念ながら、JISの規定の中には安全対策については何も書いていません。
(規格には記載がありませんが、現在は「付属書 JA(参考)使用者への指針」が最後に付属されています。)
その代わりレーザの危険性を定量化する方法や、集光させたり、発散させたりすると、危険度はどのように変わるのか?と言うことが計算式とともに細かく説明されています。
一般に生活の中で使用される工業製品であれば、必要な安全装置についての条件が詳細に記載されているのですが、研究者が実験に使用するレーザには、安全装置はほとんど付いていません。
余計な安全装置を付けられると、研究者は使いづらくて困ってしまうからでしょう。
安全装置がない代わりにレーザに対して、その出力でクラス1〜クラス4に分類をすることになっています。
この他にも、安全ラベルと貼るとか、キースイッチやインターロックを付けるとかある程度の条件が定められています。
しかし、レーザに安全対策用の保護メガネを付属することすら謳ってはいません。
これは困りました。JIS規格に安全対策が書かれていないと言うことになると、安全対策を行うには、何を見ればよいのでしょうか?
JIS規格は経済産業省の管轄、安全対策は厚生労働省の管轄になります。
縦割り行政と言うわけではなく、JIS規格は製品1つひとつに細かく対応しなければならないのに対し、安全対策は、事業所の組織で取り組むべきことであるからだと思います。
厚生労働省の通達「レーザー光線による障害の防止対策について」に具体的な対策方法が載っています。
ちなみに通達とは、お役所の本局が支局や分局に対し、仕事のやり方を指示するマニュアルのようなもので、どこの支局や分局に聞きに行っても同じ答えが返ってくることになっています。
一般に公開されていて、WEBでも見ることができるので、わざわざ、労働基準監督署に聞きに行く必要はありません。
通達は法律ではないので、法律的な根拠はないらしいのですが、どこのお役所で聞いても同じ答えが返ってくることから強制力はあると言われています。
この通達の中にはレーザのクラスごとに、取るべき対策について、しつこく書いてあります。
この「クラス」で、JIS規格と安全対策がつながるわけです。
これによって、使用者は、いちいちレーザの出力やビームの状態などを考えることなく、レーザに貼られているクラスを見て、安全対策を打つことができます。
JIS規格はレーザを作るメーカーが使うもの。通達はレーザを購入した事業所が使うものと分けることもできます。
とは言え、JIS規格に書かれているクラス分けの根拠やビーム形状による危険度の違いなどを知る必要がないかと言うと、そうではありません。
通達では、いろいろな安全対策と同様に「レーザ安全教育」も重要項目として上がっていますので、しっかり勉強しなければなりません。
(勉強の中身については、各事業所の判断に委ねられています。)
もし、レーザ安全対策を怠った場合はどうなるでしょうか?
定期的な調査や報告が義務付けられている訳ではありませんので、レーザが安全に運用されていれば、罰を受けることはありません。
しかし、レーザによる事故やトラブルが発生して、対策の不備が1回でも表ざたになると、各方面から厳しい指導や対策を求められることになり、レーザを使って実験をやるどころではなくなってしまう可能性があります。
このためにも、自己流でも良いので最低限の安全対策を行っておくことをお勧めいたします。
つづく