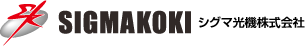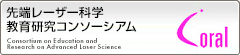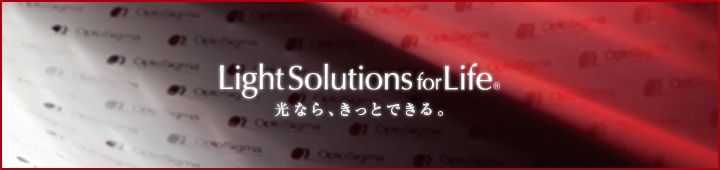
- HOME >
- コミュニティ >
- ちょっとためになる光学勉強会 >
- レーザ安全 6回目 安全対策
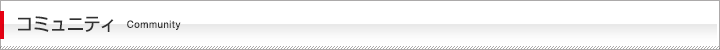
前回の話で、クラス3Rは可視光と不可視光で安全対策が大きく異なって来ると言いました。
可視光(波長400〜700nm)レーザの場合は、クラス1M、2Mの安全対策に違いがないのですが、
クラス3Rの不可視光になると、急に安全対策も厳しくなってきます。
これまでは、比較的眼に安全なレーザの話であったので、保護メガネの話が出てきませんでした。
しかし、クラス3Rの不可視光レーザでは、保護メガネが必要になってきます。
レーザ用の保護メガネは、あれば何でも良いと言うわけにはいきません。
ちゃんと、レーザの波長や光学濃度(レーザの透過率)を選定しなければなりません。
また、1つあれば十分と言うわけにもいきません。
作業に同時に立ち会う人数分用意しなければなりません。場合によっては見学者用の保護メガネも必要かもしれません。
良くあるのは、隣の部屋の保護メガネを借用してくるような使い方ですが、これも、NGです。保護メガネはレーザが設置してある場所ごとに用意しなければなりません。
危険を感じてから保護メガネを取りに行くのでは遅いのです。
また、同じ場所に3R以上の複数の波長のレーザがある場合は、レーザの波長ごとに保護メガネを用意することになります。(保護メガネによっては、2波長、3波長対応の保護メガネもあります。)
次に保護メガネの光学濃度ですが、不可視光レーザの場合は、レーザの波長を完全に遮断する完全吸収型タイプのものを選定します。光学濃度(OD)で5以上のものです。
レーザの波長によって保護眼鏡に色が付くことがあるので、特定の色が見えにくくなる場合があります。
調整作業に使用する波長変換カードまたはレーザガイド光の色や、警告ラベルやマニュアルなどの色を確認して、保護メガネをかけたままでも各々の色が見え、作業ができることを確かめる必要があります。
また、レーザ装置側にレーザウインド(YL-500)などで覆われていて、レーザが漏れてこない場合は、保護メガネを装着する必要はありません。しかし、覆いを外して作業する場合などは、保護メガネをかける必要があるので、必ず保護メガネは準備はしておかなければなりません。
保護メガネ以外には次のような対策が要求されています。
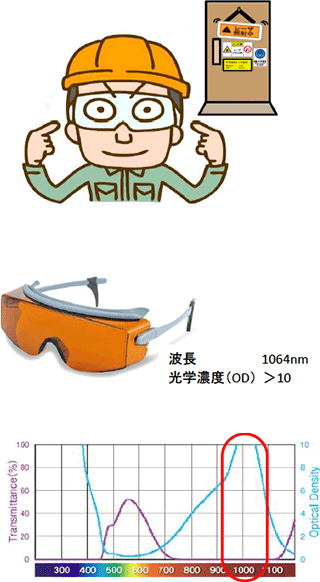
クラス3Rの不可視光レーザを使用する場合には、レーザ光が放出中であることを示す警報装置が必要になります。
厚生労働省の通達の中には「自動表示灯の警報装置を設けること。」が推奨されていますが、「レーザ照射中」と書いたプラカード(表示板)をレーザの部屋の前に掲げるだけでも問題ありません。
クラス3Rの不可視光レーザの光学系は、レーザの光路を可能な限り短くし、折れ曲がる回数を最小に減らし、可能な限り光路を遮へいすることが要求されています。
また、光学系は実験台や装置内にまとめ、レーザ光が装置を飛び出して、歩行路やその他の通路と交差しないようにしなければなりません。
「レーザ光路の末端は、適切な反射率と耐熱性を持つ拡散反射体又は吸収体とすること。」はクラス1M、2Mのレーザの光学系とほぼ同じですが、こちらはビーム径の大きさには関係なく、全てのクラス3Rの不可視光レーザの適応されます。
健康管理の面ではクラス3Rの不可視光レーザを使用する者及び、レーザ光にさらされる恐れのある作業をしている者は、視力検査に併せて前眼部(角膜、水晶体)検査を行うことが要求されています。
正確にレーザ光線による障害を特定するためには、レーザの作業に従事する前に検査しておく必要があるのですが、現実的にはなかなか厳しいと思います。
定期健診で、眼の検査を行いその変化を観察する方が現実的でしょう。
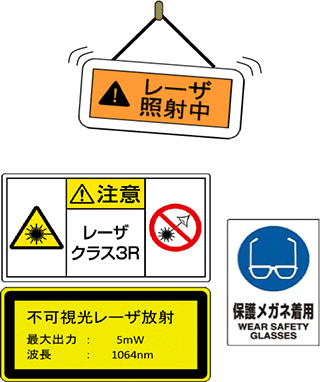
通達にはレーザ機器等の見やすい箇所にレーザ光線の危険性、有害性を掲示するとだけしか書かれていないのですが、
装置のカバーや部屋の外には右上のような説明ラベルを貼っておく必要があります。
特に、不可視光レーザであることを入室者に知らせる必要があります。
通達にはそこまで細かく謳っていませんが、JISの方には「ラベルはクラス1に対するAELを超えるレーザ放射を
人体が被ばくすることなく読み取ることができる位置に設けられなければならない。」と規定されています。
可視光レーザであればレーザビームがどこを通っているのかは誰にでも分かりますが、
不可視光レーザはどこにレーザビームがあるのかは分からないため、保護メガネをかけてから遮光カバーを開いたり、
実験室に入室しなければならないからです。
この他は、保護メガネや自動表示灯(手動の場合は不要)などが安全教育訓練や点検・整備に追加されています。
つづく